小埜 栄一郎 さん
2006年度(博士) 植物分子遺伝学
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社 研究員
けいはんなの引力

私は2000年に島本功教授の研究室からサントリー株式会社に入社しました。入社以来、製品に関わる原料作物および発酵微生物の研究に携わっています。企業研究は実利を目標にするので当然、日常生活で観賞したり食したりする実用作物が対象となります。キンギョソウに始まり、アサガオ、ゴマ、ブドウ、チャ、ホップそして酵母と多種多様な生物を相手にしてきたことだけが取り柄だと思っています。入社当時は非モデル生物を扱うことに躊躇したこともあったのですが、現代は解析機器の進展に伴ってゲノム解析や代謝物分析が容易になり、研究をするうえで大きな技術的な問題はなくなりつつあります。むしろモデル生物であるという意味が薄れてきて、セントラルドグマの解明から多様性の生物学の時代になったという感があります。
以前寄稿した当時は島本町(大阪)の研究センターに勤務していましたが、2015年に研究所が精華町(京都)に移り、再びけいはんなの地に舞い戻ってきて、この地にただならぬ引力を感じています。こちらに移ってからは奈良先端大での研究セミナーにも研究所から徒歩で赴いたこともありますので個人的には徒歩圏内ということになります。言うまでもなく奈良先端大はその所在地と集団規模においても特殊な環境です。高山町(生駒市)にいれば、実際に同じ釜の飯を食うことになるので、強い連帯感が醸成されるのだと思います。それは高山町に居るときは感じないのですが、外に出ると明瞭になります。事実、今の職場や共同研究者に奈良先端大出身者や、かつて奈良先端大で勤務された方がおられるのですが、どこか少しだけ意識して助け合っているという気がします。
研究には独創的かつ執拗な個人力と、それをサポートする体制(ヒト、モノ、カネ)の両方が不可欠であると社会に出て感じることがあります。後者にはプレゼンテーションやコミュニケーションといった技術的(スキル)な問題であることが多く、社会に出てから学ぶ機会はありますが(最近はこれを入社時で問われるようですが)、私が奈良先端大で学んだことは専ら前者です。奈良先端大でいうところのSになります。それは壁にぶつかると独創性が育まれ、面白いと感じれば自ずと持続されるというものです。逆に、結果が分かっているような実験や、本人が面白いと実感していないと研究は単なる作業になります。作業は意外で、そして重要な結果を見過ごします。これは若人の時間を費やす価値はあまりありません。しかしながら最初から面白いというのも実はありません。面白そうだな、くらいから始まるのですが、実際に面白いになるためには自分の課題周辺の知識を得て、仮説を立てて検証する実験(試行錯誤)をくり返す必要があります。つまり行為を伴う時間が要るのです。取り組む対象のどこまで分かっていて(できていて)、何が分かってないか(できていないか)を知らないと、驚きも喜びもへったくれもありません。研究をする者は知の絶壁という境界線上に立つことがスタートなので、過去の知見(既知情報)の取り込みというのは、言わば面白くなる(美味しくなる)ための下ごしらえにあたります。
科学の世界も人間が形成しているので、しっかりしがらみで溢れています。名声や賞賛、報酬に対して無関心でいることは普通できませんが、これらは研究の動機になれません。面白いの代わりになるものがないのです。これが学生の時には気付かなかったことの一つです。恩師の故・島本功教授がラボのミーティングで「めちゃくちゃ面白いなあ」と仰っていたのが今でも鮮明に脳内で再現されますが、最近読んだ本「自由と尊厳を超えて(B.F.スキナー著)」によると、この面白いという状態は研究という行為が正の強化子になったということのようです。ラボでは昔はシャーレとピペットマンだったのが今は実験道具がNGSや計算機に変わりましたが、面白いことの本質は何も変わってないと思います。私の場合は、奈良先端大で研究が面白くなったのが今の自分を形作っていると思います。そして現代の奈良先端大の後輩たちもそうあって欲しいと思います。
私が研究を続けてきて認識していることの一つに、「ヒトはシークエンシャルなロジックしか理解できない」ということがあります。風が吹けば桶屋が儲かるは、その間を取り持つストーリーがなければ意味を為しません。時間軸に沿った物事の展開を予測する能力は人類の進化にとってとても適応的な形質であったことは、たとえば、谷に動物を追い込めば食糧が得られるとか、秋に種をまけば、春に収穫できるということからも容易に想像がつきます。自宅で子供たちとNHKの「ピタゴラスイッチ」というTV番組を一緒に観ることがあるのですが、これは連続する因果が明瞭で、分かるということが何度も脳の中で起こるから面白い(気持ち良い)のだと思います。一方、生物学のデータというのは非常に断片的な情報なので、これを基にストーリーを紡がないと、意味が取れないのです。網戸の向こうの猫の喧嘩でどっちが優勢かくらいしか分からないようなものです。したがってストーリー構想力が重要になります。島本先生が「本当のところは植物に聞かなければ分からない」と仰っていたのは今でも印象に残っていますが、自然科学は一方的にヒトが自然を解釈する行為なので、究極的にはそうなのだと思います。
そうするとストーリー構想力、つまり表現力をどうやって培うかが問題になります。ニュートンのような天才は自然を観察しているだけで真理に近い因果が読み解けるのかもしれませんが、普通の人はそうはいきません。なので、偉大な先人が生み出したストーリーを模倣する、真似るのです。ストーリーは論文に限らず、小説や映画の中にも溢れています。こう言うとオリジナリティ至上主義の科学の世界ではどこか後ろめたい気持ちがしますが、解析手法はみんな真似ているのは平気なので不思議です。アナロジーと言えば少しうしろめたさが薄れるでしょうか。過去の文献を精読することは自分の研究とのつながりを考えるうえでストーリー展開に必須ですが、論文の引用文献の取捨選択自体がストーリー形成に大きな与えるので、著者によるバイアスがかかっています。さらに自分で実験的に得た断片的なデータでそこからどうストーリーを紡ぐのかとは単なる記述ではなく意識的な表現になります。そこにオリジナリティが生まれます。これは若人が時間をかけて取り組む価値のあることだと思います。映画だと観賞に時間的制約があるのと、今のところ学術論文と同じテキストで表現される書籍が適していると思います。実験の合間に、最新の文献と過去の名著と言われている作品を織り交ぜて読む。これが良いと思います。
「人々は内容を熟知していたり、今後なじむことがなさそうな本を読んだりはしない。我々が読むのは、どのみち自分がほとんど言いかけていたけれども、助けがないときちんと言えないようなことを述べている本だ。」(B.F.スキナー)
小埜 栄一郎さんの過去の記事はこちら
http://bsw3.naist.jp/graduate/index.php?id=12
(2017年10月掲載)
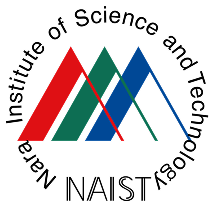 奈良先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学