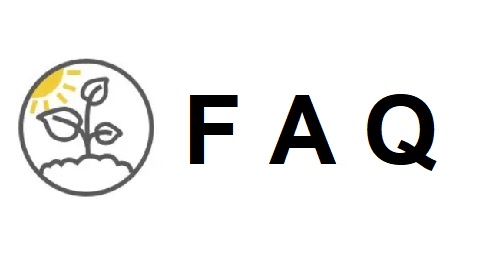当研究室への配属に興味をお持ちの方々からよく頂く質問をまとめました。
また、研究室配属・見学のページも併せてご覧ください
- Qコアタイムはありますか?
- A
時間生物学の研究者である我々はクロノタイプ(朝型・夜型など生まれつきの体内リズム特性)の重要性を理解しています。しかしながら、研究活動を円滑に進めるためには、指導やディスカッションの機会を確保し、実験計画や進捗について適切なフィードバックを受けられる環境を整えることが重要です。そのため、10 時~16 時をコアタイムとして設定することにしました。
また、大学生協の調査によると、コアタイム有りの院生の平均研究時間は修士課程で一日あたり7.8時間、博士課程で8.5時間程度、コアタイム無しの場合は修士8.8時間、博士10時間程度だとのことです。当研究室においても、週40時間程度は研究室に来て活動することを想定しています。
- Q数十分~数時間の間隔で何日分もの時系列データを取得しているみたいですが、徹夜で実験するのですか?
- A
いいえ、我々は健康も大事にしていますので、徹夜は避けるようにしています。昼夜を反転させた栽培チャンバーを併用することで、実働半日以下で24時間 or 48時間分のサンプルを集められます。また、1週間分の時系列データを取得する実験は自動化されています。
- Q植物は未経験ですが、やっていけますか?
- A
全然大丈夫です! 植物を育てるだけであれば簡単です。動物細胞の培養ほど気を使わなくてもいいですし、水は週に数回やればあとは勝手に育ってくれます。一方で、時間生物学については一定量の勉強が必要ですが、こちらについては研究室に参加してからでも大丈夫だと思います。ただ、植物の基本的な教科書については目を通しておいて下さい。プログラミング等なにか一芸があると、役に立つかもしれません。ちなみにバントが得意な学生さんもいます。
- Q生物学も未経験ですが、それでもやっていけますか?
- A
多分大丈夫です! 生物学的なバックグラウンドや実験の経験がなくても、研究への興味や前向きな姿勢があれば、十分にやっていけます。実際、時間生物学や植物生理学の知識は配属後にしっかりと身につけていく形で問題ありませんし、実験も、初めはスタッフや先輩と一緒に取り組みながら、丁寧にステップを踏んで学んでいくことができます。私たちの研究室では、未経験の方も歓迎しており、「どれだけ経験があるか」よりも、「どれだけ真剣に研究に向き合えるか」を大切にしています。地道な積み重ねの中で、計画の立て方や解析のスキル、論理的な思考力など、今後どんな進路にも役立つ実践的な力が身についていきます。
- Qおすすめの教科書はありますか?
- A
「テイツ/ザイガー 植物生理学・発生学」をお勧めします。時間生物学に特化したものではありませんが、研究室で必要な知識のほとんどは書いてあります。一般的な生物学としては「Essential細胞生物学」の内容を理解できることが望ましいです。また、「田澤 仁 マメから生まれた生物時計―エルヴィン・ビュニングの物語」や「瀧本 敦 花を咲かせるものは何か―花成ホルモンを求めて」は私たちの研究分野を理解するための読み物として面白いと思います。時間生物学についてもっと詳しいことが知りたい人は、日本時間生物学会の学会誌「時間生物学」に目を通してもいいかもしれません。
(スタッフ高橋からはcourseraの無料講座(日本語字幕有)”Circadian clocks: how rhythms structure life“と、無料教材Teaching Tools in Plant Biologyシリーズの”Rhythms of Life: The Plant Circadian Clock“の回をお勧めします)
- Q就職活動はできますか?
- A
思う存分就活してください。みなさんにはそれぞれの人生があります。私は研究が好きで研究者をやっていますが、モノづくりが好きな人もいれば、コンサルや金融に興味がある人もいるでしょう。うまくバランスをとって就職活動してくれれば、私は全力で応援します。エントリーシート等の添削も希望者には行っています。私自身に特にコネはありませんが、一緒に研究した学生さんの企業内定先の例は以下のとおりです(前職含む)。
アンズコーポレーション、大塚製薬、関西電力、構造計画研究所、JT、シノプス、千寿製薬、ソフトウェアサービス、ソライズ、大日本印刷、中部電力、テレビ愛知、東芝デジタルソリューションズ、東和製薬、トヨタ自動車、日本酵研、ベイカレント・コンサルティング、丸山工業所、ヤマトホールディングス、雪印メグミルク、りそな銀行、など。
- Q研究室の雰囲気を教えて下さい
- A
- Q研究内容はどのように決まりますか?
- A
多くの人は未経験ですので、当研究室の研究方針に関連した候補テーマの中から学生さんが選択する、という形が一般的です。学生さん同士で希望テーマが被った場合は話し合いやじゃんけんで決まりますが、基本的に人数以上のテーマを用意して、全員がいくつかの中から選べるようにしています。「私はこんなテーマについてやってみたい」、という希望があるのであれば相談してください。私たちが「それは確かに私たちが解決すべき問題だよね」と納得するテーマであればどんなものでもOKです。
- Q学会発表や学会参加はできますか?
- A
時間生物学会(秋)、植物生理学会(春)、植物学会(秋)のいずれかには参加できるようにスタッフは努力しています(お金的に)。単なる参加で終わるのか、発表するのかはみなさんの研究成果が発表に値するかどうか次第です。私としては、どうせ行くなら発表してもらいたいと思っていますので、頑張ってください!
- Q研究室にいる学生さんの1日のスケジュールを教えてください
- A
大学宿舎組&通学組の修士学生さんの例を、一人ずつ紹介します。
(「受験生のための大学案内」に掲載された内容を基に再構成)大学宿舎組 Lさんの一日 (当時M2) :「近くて便利。すぐに実験を始められます」
08:00 起床:朝食、軽い運動、読書などで過ごします。
09:30 研究室到着
12:00 昼食
13:00 実験の続き・論文を読む
18:00 宿舎に帰宅・夕食づくり
20:30 動画視聴:バスケットボールNBAを見ることが多いです。
21:30 英語やプログラミングの勉強: 世界での活動や新たな分野への挑戦に備えて
23:30 就寝
「重要な実験ほど朝早くからとりかかるため、睡眠時間を十分にとり、朝~午前中はしゃきっとしておこうと心がけています。午後はルーティン的な作業をこなすことが多いです。帰宅後は英語やプログラミングなどを勉強し、自己研鑽に勤しんでいます。」通学組 Mさんの一日 (当時M1):「オン・オフの切り替えを大切に」
08:00 起床
09:30 通学:車で20分です。
10:00 研究室到着:メールをチェックした後、実験を進めます。
12:30 昼食
13:00 実験の続き・就活のエントリーシート記入など。
20:00 帰宅:夕食、お風呂、ストレッチ、映画鑑賞などをして過ごします。
25:00 就寝
「研究とそれ以外のオンオフをはっきりさせることが大切だと思っているので、土日祝日はオフにしています。今後は、今ある課題に着実に取り組み、得られた結果から様々な可能性を導き出す思考能力を伸ばしていきたいです。」
- Qいちど見学に行きたいのですが
- A
お待ちしています。事前に希望日時やラボに来る目的(単に見たいだけなのか、話を聞きたいのか、一緒に御飯を食べたいのか・・・)をメールで教えて貰えれば、こちらも体調・財布の中身・事前準備など万全の態勢で望みます:D。過去の研究室の雰囲気を知りたいかたは、HPのほかに非公式Twitter (X)(@endolaboratory)もあります。
- Q研究室を案内してもらえますか?
- A